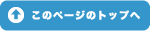メールマガジンバックナンバー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ エコニティ メールマガジン □■ 2008年8月号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ はじめに・・・ オリンピックでかなり盛り上がった8月ですが、お盆を過ぎると随分と 涼しく、雨模様の日が続いています。例年にも増して集中豪雨が頻発したり、 何とも奇妙な天候ですね。 =========================================== ◎ 目次 =========================================== 1.設備情報管理のポイント(第9回) 2.「設備管理の匠」のQ&A~その9~ 3.「北海道のうまいもん」(第9回)~柳月 きなチョコ黒大豆~ 4.エコニティからのお知らせ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1.設備情報管理のポイント(第9回) ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 前回は、リスクマネジメントを踏まえて設備情報管理をどのように実施して いくかを考えました。 その第一段階は、 「設備トラブルに起因する損害をできるだけリストアップする」事だと ご説明しました。 もちろん、完全にリストを網羅しようとすると、かなり時間がかかる作業です。 その時点で行き詰ってしまうかもしれません。 ですから、まずは思いつく範囲でも構わないと思います。 以前、設備情報管理について「運用からの逆算」ということをご説明しました。 その一番最後に「フィードバック」について触れました。 フィードバックとは、仮説を検証して、次の仮説に結びつけるプロセスです。 今回で言えばとりあえずリストアップした 「設備トラブルに起因する損害」が仮説です。 フィードバックの考え方に基づいて、定期的に運用の内容をレビューすると、 リストにない損害が出てくると思いますので、それをまた新たにリストに 繰り入れて、徐々に完全な形にしていく、ということになります。 ここで行っているリストアップとは、以前ご説明したリスクマネジメントの プロセスの中では 1)リスクを把握・特定する にあてはまります。 従って、次に来るのは「2)リスクを評価する」ということになります。 リスクを評価するには二つの要件が必要でした。つまり、 「発生頻度×影響度」 です。 このうち、まず「影響度」を考えて見ましょう。 「影響度」とは、リストアップした損害をレベル分けする、ということです。 リストアップの時点では「レベルはともかくとして、まず列挙しましょう」 ということでしたが、今度はできるだけ共通の尺度で、願わくば定量的に 損害を区分していきます。 「定量的」と言うと難しく聞こえますが、一番単純な尺度は「お金」です。 ・修繕費用 ・生産のストップによる損失金額 ・品質異常による損害金額 多くの損害は、金額換算が可能だと思います。 ですから金額換算できれば、損害のレベルを知るにはかなり有効です。 (ただ、正確な金額は実際の発生ケースによって違ってきますのである程度、 感覚的なものにならざるを得ないと思いますが) しかし、レベル分けにはそれなりに調査が必要になります。 「そんなに調査する余裕はないよ」 という声も聞こえてきそうです。 その場合には、直感的な序列をつけていく、というやり方も考えられます。 例えば、損害レベルを「A」「B」「C」や「大」「中」「小」、このように 直感的にランクわけしていく、というやり方です。 現場で序列をつけていくならば、それほど大きくはずすことはないはずです。 このように「影響度」を決めたら、今度は損害発生の「頻度」です。 もっと端的に言えば、ある一定時間内に発生した(損害発生に結びつく) 故障種類別の回数を把握する、ということです。 設備情報管理では、ここが一つの「ミソ」になります。 つまり、故障回数は何らかの形で 記録=情報 を残しておけば、はっきり 把握できるということです。 しかし、 「さあ、リスクマネジメントに取り組もう!」 と考えた時点で、きちんと記録があるかどうかはわかりません。 その場合には、損害レベルと同じように記憶を頼りにして 「このトラブルは過去にどのくらい発生しただろうか?」 ということを考えることになります。 例えば、トラブルを「多」「並」「少」、のような形で分ける、ということです。 ただ、故障回数は把握しやすい指標なので、少なくとも取組を決めた時点で 記録を残すようにして(もしくは過去の資料を分析して記録をおこして)下さい。 また、記録が整備された時点で、「フィードバック」して、記憶による区分を 徐々に修正することが望ましいと思います。 このように 「損害のレベル」と「一定時間内の発生回数」を把握していけば、リスクが評価 できます。 具体的な評価と、その後の対応についてはまた次回といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2.「設備管理の匠」のQ&A~その9~ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― このコーナーでは「設備管理の匠」によく寄せられるご質問や、上手な使い方に ついて解説します。 【Q1】 過去のデータの蓄積があります。 「設備管理の匠」を導入した場合、これらのデータを移植したいのですが、 可能でしょうか? 【A1】 最近、同様な質問にお答えしているのですが、上のような疑問を頂くことも 多いので、再度お答えいたします。 まず、過去のデータが「Excel」などの一覧表であれば、弊社で無償で 取り込むことができます。 プロセスとしては、 1)データサンプルを頂いて、弊社で取込案を策定します 2)取込案を確定させ、「設備管理の匠」本体についてご発注いただきます。 3)ご発注時点で、秘密保持契約を交わしてデータをお預かりします。 4)データを弊社で加工し、「設備管理の匠」フォーマットに変換します。 5)データと一緒にご納品。 もし、紙やWordファイル、Excelでも一覧になっていないデータの場合、 基本的には有償で取込を実施することは可能ですが、場合によっては無償と させていただくこともありますのでご相談下さい。 ~~何か取り上げて欲しい質問がありましたらメールでご連絡下さい~~ 「設備管理の匠」についてはこちらをご覧下さい。 http://www.econity.co.jp/takumi.html ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3.「北海道のうまいもん」(第9回) ~きなチョコ黒大豆(柳月)~ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 柳月の「三方六」は最近もテレビで紹介されたほど有名ですが柳月には 他にもおいしいお菓子が沢山あります! 今回はその中の「きなチョコ黒大豆」を紹介します。 きな粉&チョコ&黒大豆の組み合わせのこのお菓子・・・ 黒大豆には、現代人に必要な栄養素がたくさん含まれているので なんだか体に良さそうな気がしますが・・・ 実際に食べてみると大豆のカリカリとした食感に「あ~なるほど!」 と納得してしまいます。 この組み合わせを思いついた人は本当にスゴイと思います! カリッと香ばしい黒大豆、甘すぎないきなこチョコ 甘いのが苦手という方でも喜んで食べてもらえそうな味です。 類似品が多々ありますが、私の一番のおススメです。 お店は北海道十勝を中心に札幌、東京でも取り扱いがあるようです。 価格 1袋(80グラム) 210円 ホームページでオンラインショッピングもできます。 http://www.ryugetsu.co.jp/index.shtml ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4.エコニティからのお知らせ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■展示会について 2008年9月10日~12日に東京ビッグサイトで行われる、 「生産と設備管理のソリューション展2008」に 出展いたします。 http://www.jma.or.jp/mms/ (詳細はまた別途ご案内しております) 展示会において、点検業務支援システムのベータ版のデモンストレーションも 実施する予定です。 ご興味ある方はぜひご来場下さい。 ■デモンストレーションの対応について エコニティでは、「設備管理の匠」デモンストレーションの依頼に随時対応して います。 ご希望の方はご連絡下さい。 <問合せ先> Mail:takumi@econity.co.jp TEL:03-3865-1468 ********************************************************************** ■□エコニティについて■□ (有)エコニティは2000年に設立されました。 もともとソフトウェアの受託開発などを中心に業務をおこなっていましたが、 2003年頃から設備管理システムに取り組むようになりました。 当初は受託開発の一環としてソフト開発をおこない、その後設備保全のデータ の作成などにも関わった経験もあります。そうした経験を生かし、2005年にパ ッケージソフトとして「設備管理の匠」をまとめ、販売を開始しました。 お客様に使ってもらい、情報活用に貢献できるようなシステム作りを目指して います! URL:http://www.econity.co.jp Mail:takumi@econity.co.jp TEL:03-3865-1468 本メールマガジンが不要な場合には、下記メールまで「不要」の旨、ご連絡下 さい。お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。 編集責任者:吉村 **********************************************************************